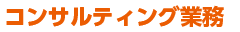保育園の運営
厚生労働省によると、保育士資格を保有しながら保育所で働いていない「潜在保育士」は75万人を超えるというデータがあります。日本国内の保育士資格者は約120万人と言われているので、約60%の保育士さんが保育士として現場で働いていないのです。また、保育士になってから3年以内に退職をする人が全体の30%、5年以内になると約50%を超えているのです。
この数字を始めて知った時には大きな衝撃を受けました。
一方で自分の将来の夢を語る子供を見た時、「保育士さんになりたいです」「幼稚園の先生になりたいです」という子供は本当に多いのです。「幼いころからこの仕事につきたいと思っていました」と言われる仕事は、数ある仕事の中でもほんの一握りです。
しかし、現実は先述の通り、潜在保育士は年々増え続け、5年以内の退職する保育士は全体の50%を超えるのです。このギャップはどこからくるのでしょうか。このギャップを埋めるためには何をすべきなのか。このことを今こそ、本気で考えなければなりません。
その大きな原因ともいえるのが、
- 「保育者が働く労働環境の問題」
- 「人材の育成・教育に関する問題」
であるものと考えています。
1、保育現場における労務管理上の問題
この問題点に関して、実際にある園長から相談があった事例をご紹介いたします。
(1)タイムカードは身支度を整えてから打刻するようにと指示していますが、ある時、職員から「着替えの時間も勤務時間ではないか?」と質問がありました。保育に入る前、終了後に更衣室でおしゃべりしている職員もいるので着替えの時間まで勤務時間にするのは難しい気がします。
(2)人員配置がギリギリの為、保育中に事務仕事が終わらず、お便り作成等を自宅に持ち帰っている職員がいます。自宅の作業なので勤務時間は把握しておらず、給与は払っていません。ただ最近、他園では賃金トラブルの原因になっている等の話も聞くので不安になっています。
(3)近頃、当園の保育士の一人が、ブログ上で、当園の体制に対する不満を書きたてたり、園長を名指して批判したりしています。これらの記載を読んだ保護者からは苦情や不安の声が寄せられています。当園としてどのような対応をとるべきでしょうか。
(4)急遽採用した主任が個性的な方で、悪気はないのですが、保育士に対し、叱咤激励するために厳しい言葉をかけることがあります。保育士の中には委縮する者もおりいい人材が当園をやめてしまうのではないかと危惧しています。どのような対処が必要でしょうか?
以上のような、労務や人事管理上のご相談を保育園の園長から数多くいただきます。このような事案には労働法や各園の運営ルール(就業規則等)に基づき、ひとつひとつの問題に対し、きちっと対処していくことが大切です。対処方法に困ったらまずはご相談ください。
社労士切り替えを検討されている方 今の社労士にこんな不満ありませんか?
- 業界(介護、保育、医療)知識が無いので的確な回答が得られない
- 賃金水準など同業他社の関連情報が得られない
- 問い合わせに対する返答が遅い
- 担当者任せでチームでの対応がない
- 給与計算や助成金手続きにミスが多い
- 労務トラブルが起きた時に頼りなかった
- 労務監査や研修講師等コンサル業務の依頼を断られた
- 情報のやり取りがいまだに紙やメールが多い
- 助成金の対応を断られた
このような不満があれば、
社労士変更を御検討ください
- 現在の当社顧問先様のほとんどが、このような問題の解消のために社労士を変更され、当社と顧問契約の締結を頂いております。
- 当社が実施する顧問先満足度調査では・・・(2022年10月実施分)
- レスポンス、相談対応力についての満足度 100%
- 業界の専門性、情報発信力に関する満足度 100%
- 社会保険手続き、給与計算、助成金に関する満足度 90%
- 現在ご契約中の顧問社労士との連絡や引継ぎについても当社が行いますのでご安心してお任せください。
当社のサービス内容
社労士変更についてのよくある質問
社労士変更手順を教えてください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
他の社労士との違いは何ですか?
当社の3つの特徴をご紹介します。
- 介護、保育、医療の各分野専門の社労士が対応
- 60事業所を超える改善事例を顧問先に展開
- 労務手続き、給与計算の他、採用支援、人事制度、研修をワンストップ対応
給与計算等の変更にどのくらいの期間が必要でしょうか?
給与計算開始までは立上げ期間として原則2か月を頂いておりますが、短縮が可能な場合もありますので、まずはご相談ください。
依頼するか迷っています。契約前に一度話を聞いてみたい。
無料相談がございます。どんなお悩みでもお気軽にお申込み下さい。
私たちが対応します!!
代表をはじめ全てのスタッフがお客様の発展、成長に向けた支援を全力で行います。



2、処遇改善加算とキャリアパスに関する課題
保育園の人材育成~こんな課題はありませんか~
新しい人材が育たず辞めてしまう
人材不足の中、縁あって入職した職員が定着せずに辞めてしまうのは残念なこと。短い期間といえど園がその職員の育成にかけてきた労力も報われません。退職理由には様々なものがありますが、もしそれが「自分のキャリアの先が見通せない」「仕事にやりがいを感じられない」ことだとしたら、それは組織の責任といえます。
施設数と職員数が増えて目指す保育が薄れている
職員数の増加に伴い、組織文化やトップの考えはだんだん伝わらなくなるもの。園が理想とする保育が職員一人ひとりに伝わっていないと感じるのであれば、これまでうまくいっていたやり方も組織の大きさに合わせて変えていかないとなりません。
昇給や賞与に人事評価を反映させたい
人事評価は行っているものの、今は給与、賞与に反映させていません。やはりこれからは目標に向けて努力をして結果を出している職員とそうでない職員とは、処遇でも差をつけたいと思っていますが、どのように反映させていけばいいのか。また職種ごとの給与水準が他園と比べてどうなのか、についても経営者は把握する必要があります。
経験年数と期待能力の格差が大きい
経験年数が長い職員は仕事への慣れから「ほどほどに頑張る」ことができるもの。ポジションの少ない保育園は特に、毎年の役割が大きく変わるわけではないので慣例に沿って仕事を繰り返すことになりかねません。新しい目標や挑戦がなければ人の成長も停滞してしまいます。
上司の期待と職員の頑張りにズレがある
どの職員も頑張っているのは間違いないけれど「各々、自分なりに頑張っている」状態に陥っていないでしょうか。管理者から見ると頑張る方向性が違うと思えたり「そういうことじゃないんだよな…」と違和感を覚えたりしてしまうのは、本人にとっても組織にとっても望ましくありません。
こんなことが考えられます。
- 組織として目指す職員像が共有できていない
- 目指す職員像があっても、そのためにどのような行動が必要なのかが明確ではない
- コミュニケーションを活性化するための道具や機会が少ない
- 目標達成や上司から認められるなどモチベーションを刺激する工夫がない
その課題、キャリアパスが解決します
3、職員育成に向けた研修
今まで多くの保育園事業所に、弊社がご提供させて頂いてきた研修の中で、リピート回数のとても多い2つの研修をご紹介させて頂きます。
(1)福祉人材人間力向上研修(保育士編)
福祉(保育)事業者にとっての最大の課題と言っても過言ではない 職員の“人間力向上”。その最大の課題を解決するためのスキルを身につけることが本研修のゴールです。
この研修を園に導入された東京世田谷のクラルテ保育園村松園長にお聞きしました。
Q、保育士の人間力向上研修も職員研修として導入されているようですが。
A、この研修は保育士である前に一人の人間として、組織人として必要なものを教えてくれる研修だと思います。「挨拶」「言葉」「笑顔」「ストローク」など、職員間のコミュニケーションと職場風土の改善に役立っています。とてもわかりやすく、シンプルに大切なことを思い出させてくれる研修で、研修成果が職員の行動変化となり表れてきています。
(2)保育園チューター職員育成研修
本研修では、実際に業務を教える立場である職員(チューター)が、OJT の理解・ コミュニケーション・育成計画の作り方等を学び、自らの役割を認識するとともに組織として新人に特化した指導体制を整備することで、早期離職防止を図り、職員の定着に資することを目的とします。
詳細は下記をご覧ください。
研修のプログラム、研修時間、受講料などは是非、弊社まで直接お問い合わせください。
人材確保対策の視点から
人材確保対策は大きく分けて人材採用、人材育成、人材定着に分けられます。
その中で最も力を入れなくてはならないのは「人材の定着」であると私は考えます。
例えば、想像してみてください。ひとつの浴槽があったとします。その浴槽には湯が溜まっていますが、栓が抜けておりどんどん湯が少なっていきます。湯量が減っていくので、蛇口から大量のお湯を入れていますが、湯は思い通りにたまりません。この現象を「湯量=スタッフ数」として考えてみると、湯を溜めるためには、まず何を優先すべきでしょうか?
重要なのは「人材定着策」
もうお分かりですね!まずは、浴槽にしっかりと栓をすることです。つまり「浴槽の栓をする=現在在籍するスタッフを離職させないこと」つまり「人材定着策」が何よりも重要なのです。どの事業所でも人材確保と言えば、求人などでの採用をメインにおいた施策を展開されますが、その発想自体、視点がずれているということになります。
現職のスタッフが辞めると、どんな影響があるか・・・ぎりぎりの人員で回している職場であれば、その負担が他のスタッフにいき、他のスタッフが疲弊し、辞めていくといった連鎖退職なども珍しくありません。また、求人活動にも風評被害の影響がある場合もあります。多くの事が、退職をきっかけに「負のスパイラル」が回ってしまうようなケースがとても多いのです。
ましてや労働力の不足により、今後はさらに新規採用が困難になることは明白です。したがって今いるスタッフの働きやすさや待遇を見直し、長く定着してもらうという事にまず主眼を置くことが、人材確保策として、最優先の「打ち手」となります。
今の保育業界全般で定着策が機能していない
次に浴槽の栓をして湯の流出が防げれば、蛇口から「湯を注ぐこと=人材の採用」により、人材確保は次第にうまく機能してゆきます。さらに、浴槽のお湯を適正な温度に保つために、「保温する=人材を育成する」という事が大切になります。
今の保育業界全般に共通して言えることは、このたとえ話の「栓」がしっかりと出来ていないこと、つまり「定着策が機能していないこと」が、より一層深刻な人材不足を招いているように思えてなりません。一番に優先すべき対策は「人材定着策」です。次に、「採用」そして「育成」ということになります。
離職要因の解消に全力を挙げる
「人材不足」に関する「社会的な環境要因」について、ただ嘆いているだけでは何の解決にもなりません。まずわれわれができることは、事業所単位での離職要因の解消に全力を挙げるべきです。人材確保対策を一挙に解決することは難しいですが、労務管理やルールの整備など、出来ることから確実に行うことで確実に効果は生まれます。
「働きやすさ」と「働きがい」とは・・・・
働きやすい環境づくりとは・・・・
保育士の性別で見ると、女性96%、男性が4%となっています。おそらく。どんな業界をみても、これだけ男性比率の少ない職場はほとんどないと思います。そのくらい、地域の子どもたちをお預かりし、生活の大半を支援する保育の仕事というのは、女性中心の世界であるという事です。
そんな女性中心の職場の最大の特徴は、結構、妊娠、出産などのライフステージによって、ライフスタイルが大きく変化する為、多様な働き方や価値観を持つ方が働いているという事です。日本の助成の就労率におけるM字カーブは改善傾向にありますが、それでも結婚、妊娠、出産そして子育てを経る中で、仕事と子育ての両立やワークライフバランスを考えたり、仕事を辞めて家事に専念するという選択をしたりします。従って、1人ひとりの価値観はもっと大切に尊重していく必要があると思います。
一方、働きがいのある職場づくりとは
 「人材定着率」は、組織の良い風土づくりと密接な関係をもっています。つまり従業員を大切にし、職場全体で「働く幸せ」を共感することができる風土を作ることが、人材の定着率につながっていきます。
「人材定着率」は、組織の良い風土づくりと密接な関係をもっています。つまり従業員を大切にし、職場全体で「働く幸せ」を共感することができる風土を作ることが、人材の定着率につながっていきます。
今まで多くの保育現場で保育士の方々とお会いしてきました。そんな中で、「働き続けたい職場」で聞かれる声があります。例えば下記のような声です。
- 「助け合える環境があって良い人がたくさんいます」
- 「先輩の○○さんにようになりたいです」
- 「園が大好きです。保護者も応援してくれています」
- 「仕事は忙しいですが、楽しくやっています」
- 「園長先生が私たちをよく見てくれていて、分かってくれているから安心できるんです」
この声を聞いていると、「やりがい」「共感」「達成感」「尊敬」「誇り」「信頼」「感謝」といった心理やキーワードが含まれているのが良く分かると思います。
それではこのように良い組織風土を持っている組織とは、いったいどのような組織なのでしょうか。昨年行ったある企業との共同研究(法政大学大学院坂本研究室とパソナキャリア社との共同研究)で行いましたが、その結果、そのような会社が共通して実行している7つのキーワードが導き出されました。
研究では、この7つのキーワードどれが欠けても本物の良い組織にはなりません。一見当たり前でシンプルなものばかりですが、実際に取り入れると多くの壁があり、時間もかかります。実際に弊社が多くのコンサルティングを手掛ける中でも強い納得感を感じております。社員の定着があまり高くない会社の方の相談に乗っていますと、確かにこの7つのキーワードの実践度合いが低いのが分かります。
7つのキーワードとは、次のようなものです。
- 社員の幸せが大切にされている
- 経営理念が実践されている
- 協力企業やお客様を大切にしている
- 理念採用をし、人材育成に力をいれている
- 話し合う風土がある
- 社内に一体感がある
- 納得性の高い人事評価がなされている
「働きやすさ」と「働きがい」を組織の中で創り上げていくこと、これは言わば「制度」と「風土」を両輪で経営を行っていくことに他なりません。多くの良い組織を見ていて、このことを実感しております。このような組織を作り上げる為には、時間がかかり、また地道な活動の積み重ねが必要にもなります。そこには、決して「諦めない」経営者の強い信念と行動力が、最も大切なことに思えてなりません。