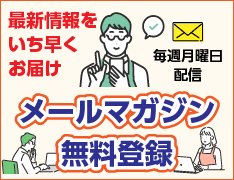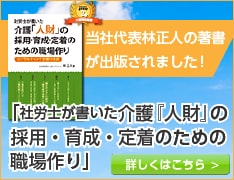クリニック・病院の現場Q&A
A、困ることはありません。クリニックにおける業務の一環として義務付けられる研修であれば、業務命令であり、興味がない程度の理由で拒否することはできません。そもそもその研修の目的や趣旨を改めて説明して受講することを促します。同時に、業務命令に従わず拒否した場合は懲戒対象になり得ることもお伝えしておきます。
【解説】
まずは、そのような職員に耳を傾け、なぜ受講したくないのか、また、クリニックとしてのこの研修の必要性をしっかりとお伝えします。クリニックが指示した研修ですので、スキルが身につく、あるいは仕事に関するノウハウや気づきが得られるなど、その職員にとってメリットはあるはずです。今回の研修を受講することで、どのようなメリットがあるかについて、職員が納得いくように話すことがまずは大切だと思います。ただ、どうしても受講しない場合には、先述の通り懲戒処分も選択肢としてはあり得ますが、まずは上記のとおり説明することで主体的に受講して頂きたいものです。
A, 法令では、1 日の所定労働時間を原則として 6 時間とする制度を導入すること
を義務付けており、7 時間とする制度を導入する義務まではありません。今後、7
時間等、6 時間以外の時間数を選択できる制度を導入することにより、必要な人
材が確保できるなどのメリットが考えられるときには、時間数を選択できる制度
の導入を検討してもよいでしょう。
詳細解説:
1.育児短時間勤務制度における勤務時間数
育児短時間勤務制度として、3 歳に満たない子どもを養育する職員について、1 日の所定労働時間を原則として 6 時間に短縮できる制度を導入することが法令で義務付けられています。なお、この勤務時間数について、所定労働時間が 7 時間 45 分の場合、5 時間 45 分の育児短時間勤務制度とすることも認められてい
ます。今回の質問は、法令で義務付けられている所定労働時間を 6 時間とする制度は導入しており、その他の時間について対応する義務まではありません。ただし、7 時間など、6 時間以外の時間を選択できる制度を導入することにより、必要な人材が確保できるなどのメリットが考えられるときには、6 時間に加え、6 時間以外の時間数を選択できるようにすることも考えられます。
2.育児短時間勤務制度の利用可能期間この育児短時間勤務制度を法令が求める子
どもが 3 歳に達するまで利用できる制度としている場合、育児短時間勤務制度の適用が終了した後に、仕事と育児の両立を図ることができない等の理由により、退職に至るというケースがあります。
育児短時間勤務制度の利用可能期間について、厚生労働省の「令和 2 年度雇用均等基本調査」の結果から最長利用可能期間の状況を確認すると、以下のようになっています。
このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしているケースが見られます。
必要な人材の確保、仕事と育児の両立の観点等から、どのようなものが職員から求められ、医院としても導入が可能であるか、現行制度を見直すきっかけにするとよいかもしれません。
3 歳未満 55.7%
小学校就学の始期に達するまで 15.0%
小学校入学~小学校 3 年生まで 11.5%
このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしているケースが見られます。必要な人材の確保、仕事と育児の両立の観
点等から、どのようなものが職員から求められ、医院としても導入が可能であるか、現行制度を見直すきっかけにするとよいかもしれません。
Q.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。
A.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
Q.新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。
A.一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく
配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその
命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で
代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要である
ことにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止
のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。
Q.採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。
A.「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件
とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが
望ましいと考えます。
A:
施設には、年休取得時期を変更できる権利がありますが、退職日までまとめて年休を取得し、退職日以降に変更する出勤日がない場合、本人からの年休取得を拒否することはできません。よって、まずは退職日が変更できないか、年休を取得しながら引継ぎに協力してもらえないか、など職員と十分話し合いましょう。また、退職の申し出自体にとてもショックをうけ、さらに追い打ちをかけるように残っている年休をしっかり使ってから辞めたい、という希望に対して法的にはやむを得ないとは理解はしつつも、感情的なわだかまりが残ってしまう辞め方になってしまうこともあります。こうした事態を避けるためにも、重要な業務を分担できる体制を整備する、日頃から年休の取得促進をはかる、などの対策を講じておくことが重要になります。
詳細解説:
1.退職日までの年休取得
日常的に年休を取得しない職員のなかには、年休が数十日も残っているというケースが少なくありません。施設には、事業の正常な運営を妨げる場合、年休取得日を変更できる「時季変更権」がありますが、退職時にまとめて年休を取得するケースでは、変更する出勤日がないため、時季変更権を行使することはできません。
そのため、まずは退職日を変更できないか本人と話し合いを行い、可能であれば、引継ぎをしながら、並行して本人の希望する範囲で年休を取得してもらうようにします。
2.退職時に引継ぎを確実に行ってもらうために
就業規則等へ「1 ヶ月前までに退職の申し出をすること」と規定している施設が多いと思いますが、年休の残日数の多い職員の退職や、1 ヶ月に1 回しか実施しない業務の引継ぎがあると、十分な引継ぎが実施できないことがあります。退職の申し出は、自身の業務内容や年休取得の予定を考慮して、場合によっては1 ヶ月前より前に行うよう、あらかじめ職員に周知しておきましょう。
また、特定の人にしかわからない業務を作らない体制や、業務内容や作業手順がわかるようなマニュアルを整備しておくなど、業務の属人化を回避し、急な引継ぎとなった場合であっても、滞りなく進められるよう、日頃から対策を講じておくことが重要です。
職員の退職時に引継ぎを確実に行ってもらわないと、後任担当者が困ることになり、ひいては利用者様へ悪影響を及ぼすことになりかねません。職員それぞれに事情があるため、やむを得ず急な退職の申し出となる場合もありますが、業務に支障が出ないよう確実に引継ぎを行いながら、本人の希望する年休取得ができるような職場づくりが求められます。
3、年休の「買い上げ」について
最後に年休の「買い上げ」に関してもお伝えしておきます。年休に関する法の趣旨を考えれば、金銭に置き換えることは年休を与えたことにはならず、違法となります。ただ、年休を法の定めのとおり付与した後、職員がこのすべてを取得せずに退職することとなった場合において、在職中の取得を選択しない職員に対し、一定の社内基準に従って金銭の給付をもって年休の取得に替えるという扱いは違法ではありません。しかしながら、法人側がこのような制度を設けていないのに、職員の方から未取得の年休を金銭給付に替えることを請求する権利はありません。年休はそもそも労働者の健康管理と余暇利用に資するために設けられた制度ですから、これを確実に取得させることが法の要請です。安易に金銭給付に替えることとするのは差し控えるべきでしょう。
A,
1 昇進の法的性格と昇進命令権
このケースで問題になっている「昇進」とは役職の上昇を意味するもので、「昇格」とは異なります。ちなみに昇格とは職務等級上の上昇を意味するとされています。ご質問のケースの昇進でありますが、特に役職者への昇進に関する人事については、管理者として能力や適性などを法人の基準で、総合的な判断で行わるものであり、また、だれを役職者として昇進させるかは、法人の経営上にも非常に重要な問題です。したがって、昇進人事については法人の広範な裁量が認められるものと解され、法人は原則として自由に職員を昇進させることが可能であると考えられます。したがって、昇進対象者には一方的な人事命令として昇進命令権を行使することが可能と考えられます。
2,昇進命令権の限界と対応
昇進は、法人に勤務している者にとっては栄誉といえる行為ですが、近時、職責へのプレッシャーなどから管理職への昇進が拒否されるような事例がみられるようになりました。
特に介護職においては、このようなケースはとても多くみられます。
このような場合、昇進を拒否する候補者を昇進させたとしても、その職責を責任をもって全うするが期待できないため、昇進を見送らざるを得ない場面もありますが、一方では、先述のように会社の人事権行使という非常に重要な権限である昇進に対すて、拒否がまかり通るようになれば、事業運営として立ち行かなくなることも明白です。
そこで、法人としては、秩序維持の観点から、昇進拒否者に対して厳しい対応、例えば懲戒処分などをとらざるを得ない場面もありますが、同時に、管理職に対する待遇の見直しなども検討し、昇進拒否といった事態が発生しないような環境づくりをしていくことも求められているのではないかと考えます。
A、報告の必要性と報告を怠った時のリスクを、職員にしっかりと説明してください。また、実際の場面では、報告すべきことが事柄と報告のタイミングや期日について院長から伝え指示をすることも必要です。
1,報告の意義と必要性を職員と共有する。
まずは、院長と職員で「なぜ報告が必要なのか」という、基本的な認識を共有する必要がありと思います。次に報告を怠った場合や報告のタイミングが遅れた場合にどのようなことが起こりうるのか、そのリスクについても共有する必要があります。
①報告の意義
報告とは、指示命令された仕事の経過や結果について、タイミングよく伝える事
②報告の必要性
・院長が仕事の進捗や質を把握できる
・不具合や問題を早期に把握し、対処ができる
・期限や患者満足度を満たせるかどうかの判断ができる
2,報告は院長から求めることが必要なときもある
仕事の報告をすることは、職員の基本的な義務です。但し、業務上の重要な判断や問題解決をしなければならない時には、院長からあらかじめ報告のタイミングや内容を職員に明確に伝えることが必要な場合もあります。特に重要な案件については、なおさらです。
従って、職員が報告を怠るとか、報告のタイミングが遅いという場合は、全て職員の責任ということではなく、院長からも適宜コミュニケーションをとりながら、報告を求めることは重要になります。
3,報告を怠ると大きなトラブルを抱えることになる
具体的にどのようなリスクやトラブルを抱えることになるのか。例えば下記のようなリスクとなります。
①仕事の期限に間に合わなくなるリスク
⇒法改正時などに必要な届出が遅れ、レセプトの請求に間に合わなくなる
②大切な職員を離職に追い込むことになる
⇒院長の目の届かないところで陰湿ないじめや嫌がらせがあったことを報告できず、職員が離職してしまう。
③感染リスクの正しい評価が出来ないリスク
⇒報告がなされなかったため、その後の感染症阻止のための対策が遅れてしまった
④患者さんや取引業者の信頼を失墜させるリスク
⇒クレームを報告せず、対応を誤ったことで患者さんや地域住民からの信頼を失う
4,リスクの予防には定期的な報告が重要になる
報告に関するリスクをあらかじめ予防するには、日頃からの職員とのコミュニケーションを密にし、定期的な報告を受けるようにそのタイミングを設定することが有効です。
また定期的な報告を待たずに、例えば「お薬について相談を受けた時」クレームを受けた時」などのように報告すべき場面を約束事として決めておくと、報告の漏れがなくなり、報告に関するリスクを予防することも出来ます。
以上
A,一般的に無断欠勤をしたという事実だけでは、懲戒処分の対象にはならず、無断欠勤をした日数や職場秩序を乱したなどの実害が発生している(または発生する恐れがある)場合に、初めて懲戒事由になるとされています。職員と連絡が取れなくなった際には無断欠勤として扱い、音信不通となった日数により超過処分を課し、「14日以上」など一定期間継続したときに懲戒解雇事由として規定します。
この「14日以上」の法的根拠に、解雇予告除外認定の基準の一つに「原則として2週間以上正当な事由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が有ります(昭和31年基発第111号)。
但し、音信不通になって2週間経過したからと言って解雇が正当と認められるわけではなく、その間、電話、メール等による「出勤の督促を行ったにもかかわらず」というプロセスを踏む(記録を残す)必要があります。それでもなお連絡が取れず30日が経過したときに,就業規則の条項に「職員が行方不明になり、30日以上連絡が取れない時」の規程に基づき、自然退職扱いとなるのが一般的なプロセスと思われます。
尚、懲戒処分には
①けん責 ②減給 ③出勤停止 ④諭旨解雇 ⑤懲戒解雇があります。
これらの規程については労基法上の制限はなく、公序良俗違反でない限り法人が自由に決められます。但し、労働契約法15条において「使用者が労働者を懲戒できる場合において
当該懲戒が、それに関わる従業員の行為の性質及び様態その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用したものとして、当該懲戒は無効とする」とさだめられており、懲戒の合理性がない場合、懲戒権の乱用と判断される場合がありますので注が必要です。
A, まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。
1.懲戒処分の根拠
懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要が
あります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うこと
ができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。
2.懲戒処分の手続き
たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを
考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。
[職員本人]
⚫ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか
⚫ 持ち出した資料はどのような内容のものか
⚫ なぜ、外へ資料を持ち出したのか
⚫ 外への持ち出しは、何回目か
⚫ 紛失していた場合、何回目か
⚫ 紛失していた場合、どのような影響があるのか
[職場]
⚫ 外への資料の持ち出しについて、普段から院
長や上司はどのように指導していたか
⚫ 外への資料の持ち出しについて、どのような
ルールがあるのか
⚫ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状
況にあったのか
懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもら
いたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。
A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。
パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。
また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。
つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。
また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。
さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。
また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。
A, 医療法16条では「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めています。病院では必ず医師が交代で夜間や休日の当直をしますが、常勤の医師が交代で行う当直業務について、労基法で言う「宿日直勤務」としての扱いができるかが問題になります。当直を夜勤(通常労働)として扱い、非常勤医師に担当させるのであれば問題ありませんが、常勤医師にたいして、日勤に引き続いて当直にあたらせた場合、労基法上の宿直勤務としていながらも労基署に許可を取っていない、あるいは許可をとっていても実態の勤務が許可基準を満たしていないケースが相変わらず多く見られます。
医師の場合、宿日直勤務とは言え、救急患者や入院患者の急変に対応しなければなりません。そこで宿日直勤務中に救急患者の対応など、通常の労働が行われる場合の取り扱いについては次のように定めています。
①通常の労働が突発的に行われる場合
救急患者の対応などの通常労働が突発的に行われることがあっても十分な睡眠時間が確保できる場合であれば宿日直として勤務することは可能。但し、突発的に行われた労働に対しては、労基法37条で定める割増賃金を支払うこと。
②通常の労働が頻繁に行われる場合
救急患者の対応などが頻繁に行われ 夜間に十分な睡眠時間が確保できないなど、常勤として昼間の労働と同様の勤務に従事することになるときは宿日直勤務の許可を取り消される場合がある。
要するに、その頻度がまれなものであって睡眠も十分に確保できるような状態であれば許可が取り消されるようなことはありません。但し、時間外割増賃金を知ら羅うことは必要になります。
注意したいのは、「まれなこと」に関する頻度です。例えば、宿日直勤務毎に毎回30分、1時間の処置当たっていた場合それは「状態」とみなされ、労基署から是正勧告を受けた例が実際にあります。従って、患者対応に時間だけではなく頻度も含めて「まれなこと」であるかどうかを判断されることになります。
対応策としては、医師の当直について、アルバイトの非常勤医師に当直を委託している民間病院は相当数あります。非常勤医師に委託する場合は、土日のみ、2次救急の輪番時のみに委託したり、病院に事情により異なります。
当直を非常勤医師に委託する場合に問題になりやすいのが「入院患者の急変に誰が対応するか」です。多くの病院では当直医がそのまま担当するようですが、患者によっては主治医の指示を仰ぐ必要もあり、主治医は実質的にオンコール体制におかれているとも言えます。
そのため常勤医師にタブレット端末を支給して院外でも画像や検査データが観察できるようにし、当直に非常勤医師に必要に応じて指示を出し、救急体制を維持している病院もあります。
その他、勤務交代による「チーム体制」にすることで、当直明けの勤務を非番として
連続当直を禁止している病院や、当直翌日は半日勤務にしたり、手術数を調整したり外来数を制限したりして連続勤務の負担を軽減している病院もあります。ただ、それには十分な人員確保が必要になる等の課題はありますが、勤務医の負担軽減に一定の効果を上げている病院もあります。