コラム
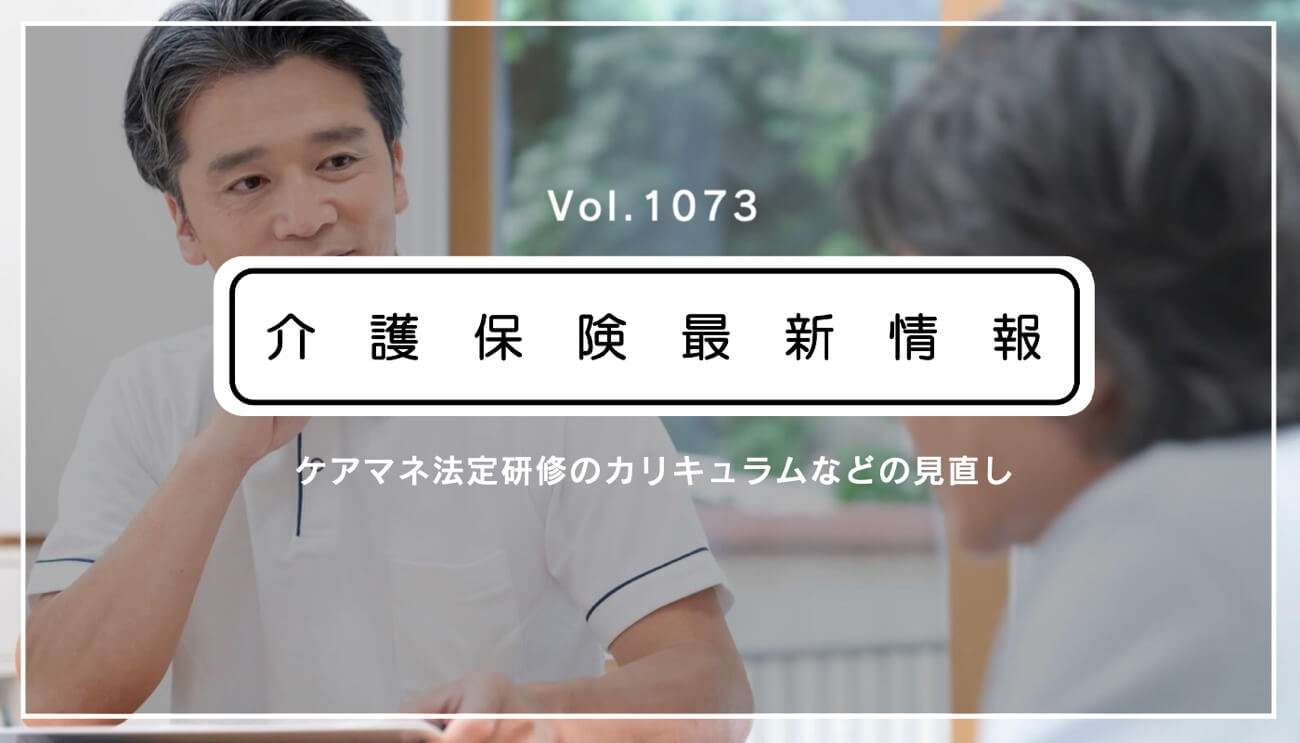
《 介護保険最新情報Vol.1073 》
厚生労働省はケアマネジャーの法定研修のカリキュラム、ガイドラインを見直す方針だ。28日、その見直し案を伝える通知を発出。介護保険最新情報のVol.1073で、自治体や現場の関係者らに広く周知した。
今回の見直し案は、厚労省が昨年度の事業(老人保健健康増進等事業)で有識者らの協力を得て作成したもの。あくまで"案"で確定ではないものの、これが新しいカリキュラム、ガイドラインのベースとなる。
ケアマネの法定研修はどう変わるのか。厚労省は通知で、カリキュラムの「見直しのポイント」を紹介している。実務研修、専門研修、主任ケアマネ研修などのポイントを記事下にまとめた。詳細は介護保険最新情報のVol.1073で確認できる。
厚労省は通知で、「今後のカリキュラム・ガイドラインの改正、施行に向けたスケジュールについては、全国担当者会議の開催などを通じて随時お知らせしていく」とアナウンスした。
=====
■ 各研修共通の見直しのポイント
◯ 幅広い視点で生活全般を捉え、生活の将来予測や各職種の視点・知見に基づいた根拠のある支援の組み立てを行うことが介護支援専門員に求められていることを踏まえ、そのような社会的要請に対応できる知識や技術を修得できるように科目の構成・内容を見直す
◯ 介護保険以外の領域も含めて、制度・政策、社会資源などについての近年の動向(地域共生社会、認知症施策大綱、ヤングケアラー、仕事と介護の両立、科学的介護、身寄りがない人への対応、意思決定支援など)を定期的に確認し、日々のケアマネジメントの実践のあり方を見直すための内容の充実・更新を行う
◯ 法定研修修了後の継続研修(法定外研修、OJTなど)で実践力を養成することを前提に、カリキュラムの内容を幅広い知識の獲得に重きを置いた時間配分(=講義中心)に見直す
■ 実務研修の見直しのポイント
◯「人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理」の時間数増
◯「居宅サービス計画等の作成」「サービス担当者会議の意義及び進め方」「モニタリング及び評価」の時間数減
◯「地域包括ケアシステムの深化及び地域の社会資源」の時間数増
◯ ケアマネジメントの展開に関する科目の事例類型の見直し
◯ 制度・政策、社会資源などについての近年の動向に関する内容を反映
■ 専門研修Iの見直しのポイント
◯「ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定」の時間数減
◯「ケアマネジメントの実践における倫理」の時間数増
◯「個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習」の時間数増
◯ ケアマネジメントの演習に関する科目の事例類型の見直し
◯ 制度・政策、社会資源などについての近年の動向に関する内容を反映
■ 専門研修IIの見直しのポイント
◯「ケアマネジメントの実践における倫理」の新設
◯ ケアマネジメントにおける実践事例の研修・発表に関する科目の事例類型の見直し
◯ 制度・政策、社会資源などについての近年の動向に関する内容を反映
■ 主任介護支援専門員研修の見直しのポイント
◯「終末期ケア(エンドオブライフケア)を含めた生活の継続を支える基本的なマネジメント及び疾患別マネジメントの理解」の新設(現行の「ターミナルケア」は本科目に統合)
◯ 制度・政策、社会資源などについての近年の動向に関する内容を反映
■ 主任介護支援専門員更新研修の見直しのポイント
◯「ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援」の新設
◯ 主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導、支援の実践に関する科目の事例類型の見直し(介護ニュースJOINT)
厚生労働省は27日の厚生科学審議会の分科会で、4回目の新型コロナウイルスワクチンの接種について、その費用を公費で賄う予防接種法上の「特例臨時接種」に位置付けた。
対象は60歳以上の人、18歳以上で基礎疾患がある、または重症化リスクが高いと医師が判断した人とした。医療従事者や介護従事者も、これに該当しなければ対象に含まれない。
厚労省は今後、自治体との調整を進めつつ5月末の接種開始を目指す考えだ。
4回目の接種で使用するワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製の2種類に決めた。接種間隔は3回目の接種から5ヵ月以上。基礎疾患がある人については、呼吸器や心臓、腎臓、肝臓の慢性の病気、糖尿病、がんなどで通院・入院していることを条件とした。また、BMIが30以上の肥満のケースも含めた。
接種券はまず、60歳以上の全ての人に送付する見込みだという。一方、基礎疾患がある18歳以上の人などは自治体が把握できていないため、本人が申請する"手上げ式"での対応を想定している。
これまでの海外の研究によって、ファイザー社製を4回接種した60歳以上の場合、3回接種した人よりも一定の重症化予防効果が得られた一方で、感染予防効果は短期間しか得られなかったと報告されている。そのため厚労省は、今回の4回目接種の目的を「重症化予防」と設定。対象者の選定も、あくまで重症化リスクの高さを基準として行った。
後藤茂之厚労相は27日午後、「5月末から4回目接種を開始できるよう必要な手続きを進めていく」と記者団に説明。「明日、自治体の担当者向けに説明会を開催する。引き続き緊密に連携しつつ準備に取り組みたい」と述べた。(介護ニュースJOINT)
笑いには「医力(いりょく)」がある――。
医学博士の高柳和江さんと、
2021年4月13日に逝去された
筑波大学名誉教授の村上和雄先生は、
そう提唱されていました。
医学と遺伝子工学、
異なる見地から放たれる〝笑い〟の
知られざる効用に目を見開かされると共に、
笑顔でポジティブに生きる大切さを教えられます。
ユーモアを武器に、
力強く朗らかに生きたいものです。
☞
〈村上〉
ストレス社会と言われて久しいですが、
私はストレスにもポジティブ・ストレスと
ネガティブ・ストレスがあると思いました。
問題にされているのはネガティブ・ストレスで、
それが加わると血圧や血糖値が上がったりする。
では、喜びとか感謝とか、笑いとか、
ポジティブなストレスを加えたら
下がるのではないかという仮説を立てたんです。
こういうことを考え始めた時に、
偶然吉本興業の社長に出会うんですよ。
〈高柳〉
ご縁ですね。村上先生が吉本興業と組んで
笑いが体に与える影響を調べられていたのは、
私は本当に画期的なことだと思っていたんです。
〈村上〉
実はそれまでは、吉本なんて全然見たことがなかった(笑)。
だから、すべては偶然の出会いから始まったんですよ。
〈高柳〉
あれはいつ頃から始めたのですか。
〈村上〉
2002年ですね。
みんな、遺伝子と吉本なんてミスマッチだと思ったはずですが、
そうじゃなかったんですね。
科学は知的なエンターテインメントだから。
まず、笑いによって血糖値が下がると仮定して、
糖尿病のお医者さんのところに
「こういう実験をやりたいんです」と相談に行ったら、
ほとんどのお医者さんから
「それはちょっと……」と断られました。
まあ、そんなアホなこと、まともな医者はやりませんよ。
ただ、私たちはアホだったから(笑)、
私の教え子の関係で半ば無理やり
協力してもらって実験を開始しました。
やってみて分かったのは、
笑いは科学にしにくいということです。
よく「笑いのツボ」とかいいますが、
東京の奥様と関西のおばちゃんでは、
笑うところが違うんですね(笑)。
そういう地域差もあるし、年代差もある。
だからどうしたら科学になるかを考えて、
2日に分けて実験をすることにしました。
対象は糖尿病の初期の患者さん二十数人です。
1日目は軽い昼食後、
大学の先生による「糖尿病について」
という講義を聞いてもらったんです。
特に下手な話をお願いしたわけじゃないですよ(笑)。
先生にはいつもどおりの講義をしてもらった。
すると、食前に測った血糖値よりも、
平均で123㍉も上がったんです。
上がる人は200以上も上がった。
これは予想以上でした。
だから、血糖値の高い人は
つまらない話を聞いちゃダメなんですよ(笑)。
2日目も同じ昼食を取ってもらった後、
同じ時間から漫才を聞いてもらいました。
そうしたら笑いによって平均77㍉下がっていたのです。
(月刊 致知より)
「不適切保育」という言葉があります。文字どおり不適切な保育のことですが、主に子どもを身体的あるいは心理的に脅かしたり傷つけたりする保育のことを指しています。「虐待保育」とも言われます。筆者がアドバイザーをつとめる「保育園を考える親の会」に寄せられる相談にも「不適切保育」が心配される例があります。
■「しつけ」なのか「虐待」なのか 例えば、3歳児がトイレに行く時間を決められていて、その時間以外に行きたいと言ったり、そのとき出なくて後でお漏らししてしまったりすると激しく叱られたり罰を与えられたりする、という事例があります。
保育者の側からは、バラバラに行かれると安全を把握できないのでルールを決めていて、守らせるために叱っているのだろうと思います。保護者はそのように説明されれば、「しかたがない」「しつけだから」と考えてしまいがちです。 しかし、このような保育には問題があります。激しく叱られたり罰を与えられたりすることで、子どもの心が深く傷つけられてしまうことがあるからです。トイレに閉じ込められたことがPTSD(心的外傷後ストレス障害)になり、その後しばらく一人でトイレに入れなくなったお子さんもいました。
そこまでのことはなくても、子どもがトイレを強制されて苦痛を感じていたり、お漏らしを人前で叱られて自尊心を傷つけられていたりしていたら、保護者としてはいたたまれない事態だと思います。 排泄の自立には個人差があり、それぞれのペースが尊重されなくてはなりません。オムツがはずれた子どもでも、遊びに夢中になるとトイレに行くのを忘れてしまったり、先のことを予測してトイレをすませるのは難しかったりする場合は多いものです。
保育内容の基準を示した「保育所保育指針」には、それぞれの子どもの発達や個性に応じて排泄も含む生活習慣を無理なく身につけていけるよう、保育者が適切にかかわることを求めています。 集団生活であっても、やり方次第で一人ひとりの気持ちを尊重する保育はできるはずです。「不適切保育」は、保育者の資質もしくは園の体制が不十分である場合に表れやすいといえます。 ■乳幼児だからこそ気をつけてあげたい 乳幼児期は「人格形成期」と言われますが、子どもは親や保育者などの身近な存在に認めてもらったり共感しあったりすることで、自分をかけがえのない存在、大切な存在と感じることができるようになります。保育では、そんな発達上の特性も配慮しながら、子どもの人格を尊重する保育を行うことが求められます。
乳幼児はつらかったり嫌だったりしても、それを大人にうまく伝えることができません。それに、園での保育者は子どもにとって大きな存在なので、保育者の反応は子どもの心に大きな影響を与えます。 保育者は専門職なので、そんなことは理解しているはずなのですが、現場の余裕のなさや自身の勉強不足から、無自覚のまま、子どもに対して不適切な対応をしてしまう場合があります。 そんなときは、施設長や保育者のチームが自分たちで気づいて保育を正してもらわなくてはなりませんが、保護者も疑問に思ったことがあれば、保育者や施設長に伝えて、保育の考え方を確認することも必要です。
■「不適切保育」の定義 では、どんなことが「不適切保育」に当たるのでしょう。 全国保育士会がまとめた「保育所・認定こども園における人権擁護のためのチェックリスト」は、不適切と考えられる保育者のかかわりを次の5つのカテゴリーに分けて掲げています。 ①子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり ②物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ ③罰を与える・乱暴なかかわり ④一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり
⑤差別的なかかわり このチェックリストには、これにそって具体的な場面を挙げているので参考になります。 保育には流れがあり、子どもと保育者の関係もいろいろですので、一律には判断できない部分もあります。保育者が危険な場面で子どもを大きな声で制止したり、子どもの気持ちを考えつつ諭したりすることが悪いわけではありません。保育が不適切なのかどうか、議論が分かれる場合もあるでしょう。 ひとつ指標にできるのは、「大人がされて嫌なことは子どももされたくない」ということです。子どもも体は小さくても大人と同じ人格をもった存在です。「子どもの人格を尊重する」とは、それぞれその子どもなりの発達のプロセスがあり思いがあることを理解して、目線の高さを同じにして接するということです。
■実際にはこんなことが… 不適切であると明確に言える保育をあえて例示すると、次のようなものがあります。これらは、実際に保育現場で不適切と指摘され問題にされたことがある保育者の行為です。 ・たたく、強く引っ張る、長い時間立たせる(座らせる)などの体罰。 ・罰として、部屋の外に出す、閉じ込めるなど。 ・罰として、食事やおやつなどを与えない、取り上げるなど。 ・「バカ」などの暴言で叱る、感情的に怒鳴る、恫喝するなど。
・子どもを集めて「○○ちゃんはお片付けしなかったんだって」などと「吊し上げ」の形で罰する。 ・子どもの身体的特徴をからかう。 後半は大人に対するハラスメントとも共通しています。さらに、例えば保育者がふざけて子どもを面白い格好や髪型にして、「かわいい」などと保育者同士で笑い合っているのも、子ども自身が楽しんでいなければ、ただの「からかい」でしかないと思います。 もしも、わが子の通っている園で「不適切保育」ではないかと疑われることがあれば、保護者は勇気を出して確かめてみてください。
保育者の心配な対応を見かけたり、子どもが家で気になることを言っているというときは、連絡ノートや送迎時の対話で不安を伝えてみるのもよいでしょう。よく学んでいる保育者であれば、気づいて修正してくれるはずです。 何か別の意図がある場面をこちらが誤解していることもありますので、最初は「こういうときはこうされているのですか?」など、保育の方法や方針をたずねるソフトなアプローチがよいかもしれません。 本人には直接言えないような決定的場面を見てしまったときは、主任や施設長に相談してみることをお勧めします。事実を確かめて、必要な指導をしてくれるはずです。
問題があるのかどうか自信がない場合は、ほかの子どもにも同じようなことがないか、ほかの保護者とコミュニケーションをとってみてください。父母会(保護者会)などの保護者組織がある場合は、父母会を通して確認したり要請を行うことも有効です。 「不適切保育」が大問題になったある園では、園の側が事実を認めないため、保護者がレコーダーで録音し、市役所に提出したということもありました(録音などは無断で公開したりすると違法になることもあるので注意)。
■行政に訴えることも 「不適切保育」の事実があるのであれば、都道府県や市区町村などの自治体はこれを指導する責任があります。市区町村は保育の実施主体ですし、都道府県は園を認可したり指導監査を行う立場にあります。 市区町村は各園と日常的な業務連絡がありますので、相談しやすいでしょう。たまに「外形的基準を満たしているので、指導できない」「民間には口出しできない」などと言われる場合もありますが、そのときは「『保育所保育指針』や『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』に違反しているのではないか」と言ってみてください。
「保育所保育指針」は保育内容についての基準を示したものです。幼保連携型認定こども園の場合は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」がこれにあたります。 また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第9条の2には、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、(中略)当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と、不適切保育や虐待を禁止する規定があります。 市区町村の窓口で納得のいく対応が得られなかった場合は、都道府県の指導監査部門に相談してみてください。市区町村に指導を促してくれる場合があります。
保育内容についての相談は、つかみどころがないと思われてしまいがちです。①自分の推測と事実は分けて話す、②それが子どもにどのような不利益となっているかを話す、③証拠になるものがあれば提示する、などの訴え方を考えてみてください。 「不適切保育」が発覚した場合に園や自治体がとるべき対応について、「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」(厚生労働省 令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 実施主体 株式会社キャンサースキャン)に示されています。
「不適切保育」が発生した園は、原因をさぐり再発防止策を立てるとともに、職員全体の人権意識の向上や、保育を振り返り質を高める取り組みを計画的に進める必要があります。そのような事後の対応策も、自治体が指導することが求められます。保育は、国や自治体の責任で、子どものために提供するものだからです。 ■子どもの心のケアも 子どもの心への「不適切保育」(特に恐怖体験など)の影響が心配される場合は、児童精神科や臨床心理士のいる支援機関などの専門機関で受診することをお勧めします。
心の傷が大きなものだった場合、思春期になってから影響が表れる場合もあります。ていねいに診てくれる機関であれば、子どもの怯えなどについて、保護者や保育者などの周囲がどう対応すべきかなどの助言もしてくれるはずです。 「不適切保育」は、子どもの心を傷つけるだけではなく、他者に対して暴力やハラスメントを用いて問題解決をするという誤った行動見本を子どもに学習させ、人権侵害の輪を広げてしまうことにもなりかねません。子どもの人権侵害は、大人たちが協力しあって防止していくことが必要です。(4月23日 東洋経済 オンライン記事より)
A 休職制度を設けるのであれば、休職と復職を命じるかどうかを判断する上での、公正な客観的な判断基準が必要です。その他にも就業規則に盛り込むべき内容は下記になります。
①休職について
・休職を命じる職員に要件
・休職を命じる判断基準
・休職期間
・休職中の賃金
・休職中の留意点
②復職について
・復職後の働き方
・復職を命じる判断基準
③休職期間完了時の取り扱い
上記の中で、休職を命じる判断基準では、例えば、「診断書の提出」はもちろん、「回復に何年もかかる場合には休職は命じない」または「業務外の同じ傷病が理由で欠勤と出勤を繰り返すようなときには休職は命じない」など、状況を想定しながら規定に落とし込んでいく作業が必要となります。休職期間については、「休職期間中であっても園は社会保険を負担しなければならないので、これまでの貢献度合いを考慮し、勤続年数が長い職員と短い職員では差を設ける」ことも大切です。
復職については、復職を命じる判断基準は、本人の復職願いの提出の他、主治医の診断書、
本人との面談実施や園指定の医療機関の受診なども必要です。また、復職後、もし同じ傷病で欠勤した場合には復職を取消、直ちに休職を命じることとし、休職期間は、前の休職期間と通算すること等の規程も必要です。
休職期間満了後の取り扱いについては、回復を見込んで休職を命じたけれど、回復できない場合には、残念だけど退職とせざるを得ない、ということで、休職期間満了日をもって
退職とします。
まずは、上記の内容を規定に明記しておくことで、いざというときには、冷静に対処できるようになります。
☞
社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
いちばん近い人を、いちばん大切にする
家族の中に、愛や理解、平和があったなら心の病やストーカー、DVなど、多くの問題はうまれてこなかったでしょう。
「夫婦だから」「親子だから」「兄弟だから」なんにもしなくても気持ちは通じ合うはず。イライラしたり、不機嫌でいても、感情をだしても許してもらえるはず。だから外での付き合いをたいせつにしたり、人脈を広げたりすることの方が大切なはず、と。
でもそれは誤解です。
家族とはもともと形態があるものではなく、自分たちで、こころをかけて作っていくものものです。安定した関係を作るには、それなりの時間とエネルギーが必要です。
近い人との距離感は、近いからこそ難しいものです。近いからこそぶつかったり、面倒だったりします。それでも心を砕いて、相手に寄り添うことが必要なのです。
自分のことを理解してほしいならば、相手のことをまず理解しましょう。
一緒に食事をとり、一緒に話をしましょう。相手の問題を一緒に解決しましょう。
嬉しいことも共有しましょう。
愛する人たちと笑顔の時間をすごせることほど、幸せなことはないと思います。
いちばん身近にいる人が、自分を理解してくれることほど、幸せなことはないはずです。
自分を大切にしようと思ったら、いちばん近い人を、いちばん大切にすることではないでしょうか。
☞
福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
A, 2年に時効により消滅した未消化有休、退職による請求不可能になる残余有休の2つの場合に限り、買い取ることを認められています。但し、買取のルール化をするのは避けておいた方が良いでしょう。
まず、年次有給休暇の買い上げについて行政解釈をみると、
「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求しうる
年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である」
つまり、買い上げを認めてしまうと、買い上げることを理由に職員からの有休休暇の請求を拒んだり、金銭目当てに有給休暇をあえて取得しないということが起こり得るからです。しかしいかなる場合にも認めないかというとそうではなく限定的に買い上げが認められています。それは次の2つの場合です。
1,時効により消滅した未消化年休
2,退職や解雇により請求不可能となる残余年休。
退職日までの未消化の有休をすべて請求されてしまうと「他の日にしてくれ」という時季変更権を行使する余地がなく、原則申請されたものを与えるしかありません。買い上げる場合でも、退職時あるいは退職後に有給休暇の残日数に応じて金銭が支払われるものであれば違反とはなりません。
⇒
社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
政府は介護事業者の煩雑な手続きの見直しを検討する
政府は介護保険事業者の行政手続きの簡素化に乗り出す。自治体ごとにばらばらな書式の統一やデジタル化の促進などの是正策を検討する。業界では人手不足が慢性化している。余計な事務負担をなるべくなくし、本来のサービスに経営資源をより多く割けるようにする。介護の質を維持しながら、効率的な働き方に移行するよう促す。
18日の規制改革推進会議の作業部会で提起した。今後、厚生労働省や総務省などと協議し、対応策をまとめる。
介護事業者は都道府県や市区町村にさまざまな書類を提出する必要がある。広域展開する大手の場合、200近い自治体に同じ内容を届け出た事例もあるという。負担は膨大だった。
役員や介護報酬が変わる際などには届け出が求められる。自治体によっては経歴や組織図、誓約書などが必須で、押印が要るケースもある。介護のローカルルールと呼ばれ、地域ごとに細かな違いが多い。
電子申請などのデジタル対応も進んでおらず、紙の手続きがなお残る。自治体ごとに別々の書類をそろえるのは手間で、政府に改善を求める声が出ていた。
18日の会合では日本在宅介護協会が煩雑な事務の実態を紹介した。自治体に報告する際に毎回、書類の作成やコピー、宛名書き、封入、投函(とうかん)などといった作業がいちいち発生しているという。
提出する書類の内容や様式も自治体ごとに異なる。例えば千葉県香取市では変更届に加えて勤務形態の一覧表などの書類が必要だ。同じ県内の成田市では社員の経歴書や職員の配置表なども求められる。押印や郵送のしきたりが残る自治体もある。内閣府によると、社長交代時に数十、数百の届け出が必要になる事業者もいる。
介護保険制度が始まった2000年前後は、地方分権一括法の成立など分権の機運が高まった時期だった。介護事業を市町村の自治事務と位置づけて地方の裁量に任せた負の側面として、非効率な事務手続きが残った。
デジタル対応が遅れている市町村も多く、オンライン申請も普及していない。牧島かれん規制改革相は会合で「デジタル時代において合理的でなく、地方分権がめざしてきた姿でもない」と指摘した。
規制改革会議は現行制度の見直しを急ぐ。まず書式や添付書類の統一を検討する。一つの自治体に提出すれば、他への提出を不要にするといった簡略化措置なども議論する。
事業者の負担軽減に加え、自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速するきっかけにもなるとみる。自前の対応が難しい小規模な市町村などを念頭に、国が開発した電子申請システムの導入拡大策についても協議する。(日本経済新聞 朝刊 経済・政策2022/4/19)
A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。
弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。
- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。
評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。
- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。
評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。
その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。
⇒
①医療分野キャリアパス
クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
②介護分野キャリアパス
処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
③保育園のキャリアパス
保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
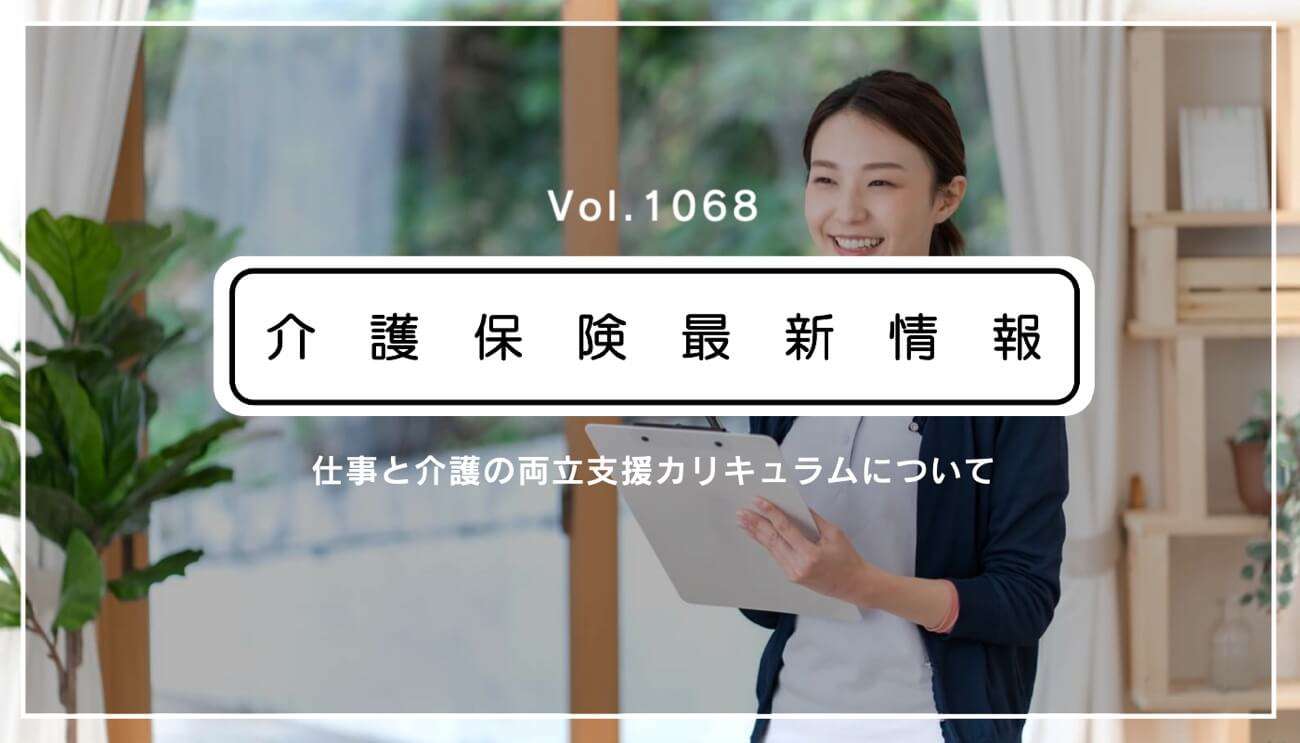
《 介護保険最新情報Vol.1068 》
仕事と介護の両立という観点から利用者の家族を支援する場合、どんな視点を持って臨めばいいのか。
厚生労働省は既にケアマネジャー向けの研修カリキュラムを策定済みだ。21日、介護保険最新情報のVol.1068を出してその内容を改めて周知。自治体の担当者や居宅介護支援の事業者、ケアマネジャーなどに積極的な活用を重ねて呼びかけた。
厚労省の「仕事と介護の両立支援カリキュラム」は、いわゆる「介護離職」の防止に向けて2020年度に策定されたもの。内容は多岐にわたるが、例えば家族が働いているケースの支援の視点、育児・介護休業法の活用も踏まえたケアマネジメントの方法などを、具体的に学ぶことができる。カリキュラムの冒頭には、「ケアマネジャーがケアマネジメント業務を行う中で、利用者が望む生活、自立した生活に大きく影響する家族が抱える課題に目を向けることも大切」と改めて記載されている。
厚労省は昨年度、このカリキュラムを用いてモデル研修の実施や講師の養成などを進めてきた。今回の通知ではこうした取り組みを報告。あわせて「今後、介護支援専門員の法定研修のカリキュラム改正を予定しているが、この内容も盛り込まれる予定」とアナウンスした。(介護ニュースより)





