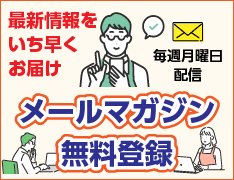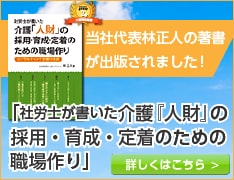「自宅で保育する人にも手当」出す国のホンネ~賛否両論あるがフィンランドの凄い政策
2018年から2022年にかけて、5年連続で「幸福度ランキング世界一」を達成したフィンランド。その背景にあるのは、“人こそが最大の資源で宝”という哲学。立場を問わずすべての国民が平等に、そして幸福に暮らすことを可能にする、「仕組み」とは――? そして、日本はそこから何を学べるのでしょうか? 『フィンランド 幸せのメソッド』より一部抜粋し再構成のうえお届けします。本稿では、子育て世帯を支える保育制度を中心に紹介します。
■親を支える保育所 フィンランドの保育には、日本の保育園のような「集団保育」と、保育士が自宅で自分の子どもを含めて4人までを預かる小規模な「家庭的保育」の2種類がある。 全体の約8割が集団保育所を利用しており、家庭的保育は7%ほどだ。家庭的保育は最近では減りつつあるが、家庭的な雰囲気の中で保育をするため、3歳未満の子どもを持つ親や、短期間だけ保育が必要な場合に人気がある。 一方の集団保育所も、国の基準で3歳未満は子ども4人につき最低1人の保育専門職、3歳以上は7人につき1人以上の保育専門職が必要だと定められており、少人数制だ。他にベビーシッターや家族、親戚に頼るという選択肢もあるが、その割合はそれほど多くはない。
1996年に改正された保育園法に従って、自治体には全ての子どものニーズに応えられるよう保育所を確保する責任があり、夜勤やシフトワークによって昼間以外の時間に働く人のためにも保育所が用意されなければならない。 保育の申し込みは通常4カ月前までに行わなければならないが、急な仕事や就学、資格取得等のために保育が必要となった場合には、2週間以内に自治体はサービスを確保する義務があると定められている。 ただ、希望の保育所に必ず入れるわけではなく、エリアによってはギリギリの数しかないため、仕事の内容によっては優先順位がつけられて待たされることもある。
教育は大学院まで無料のフィンランドだが、保育は無料ではない。日本と同じく、料金は所得に応じた金額となっている。それでも、子どもの年齢にかかわらず、利用料の上限は月288ユーロ(2021年)と比較的手ごろな価格となっていて、逆に所得が低い場合は無料となる。 また、多くの保育所では朝食と昼食が無料で提供されている。朝食はおかゆのようなオートミールなどシンプルなものだが、ただ子どもを起こして連れていけばいいだけなのは楽だ。
ただし、朝食サービスを利用するには早くに行かなければならないため、私の友人の多くは家で食べさせた方がいいと、サービスを利用していない。さらに、保育所に預けられる時間は最長で10時間と決められているため、残業をしている余裕はなく、親は定時で仕事を切り上げて迎えに行くことが求められている。 ■インクルーシブの方針 保育所は、毎日フルタイムで利用する人もいれば、週に何回か、あるいは半日だけの利用の人もいて比較的多様だ。また、フィンランドでは障がいがある子どもも、そうでない子どもも、同じように共に学ぶことを目指すインクルーシブの方針を採っている。障がいがあっても地域の保育所に通えるし、健康上の理由で通うのが難しい場合は、自宅に保育士が来て幼児教育が受けられる。
しかし、全てがうまくいっているわけではない。緊縮財政による保育士不足は深刻で、2016年には3歳以上の子どもに対する保育士の割合を、従来の子ども7人あたり1人から、8人あたり1人へと一旦引き上げたり、親の就業状況によっては保育所に預けられる時間を制限したりした。 しかし、2019年に社会福祉の充実を目標としている社会民主党が政権に返り咲き、人数や時間の制限は以前の状況に戻った。そうした動きの一方で、現在では保育の無償化や5歳からの幼児教育の義務化の議論も行われ、実際、全国規模の実証実験も行われている。
保育所と同じぐらい大切な親への支援制度が、「在宅保育の休業制度」だ。子どもが3歳になるまでは仕事を休んでも職場が確保され、復帰後に必ず同じポジションに戻ることが保障されるというものだ。 休業補償が出る育休は子どもが1歳になる頃に終わるため、通常はこれが仕事に復帰するきっかけとなる。しかし、この在宅保育の制度があるので、もっと子どもと過ごしたいと望めば、最長3年間、父親でも母親でも安心して休むことが可能だ。
私の友人も、この育児休暇取得中に所属先の会社で大掛かりなリストラがあったが、「私が元に戻る権利は法的に保障されているから、絶対にリストラにあわない」と断言し、子育てに専念していた。 在宅で保育をしたら、その間には保育所を利用しないことになる。そこで、在宅保育をしている親に国からお金を給付する「在宅保育手当」も1985年に誕生した。 この制度が生まれた背景には、施設での保育のニーズがそれほどなかった農村部から、保育施設を利用している都会の人たちにばかり税金が費やされ、自分たちには何のメリットもなく不平等だという訴えがあったことが影響している。都市部の自治体にとっても、手当を出すことで在宅保育が増えれば、保育所の利用が減るというメリットもあった。
⇒
社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
保育は自治体にとってかなりのコストがかかるので、在宅保育をする親には国からの在宅保育手当に加え、多くの自治体が独自に手当を支給してきた。 ■自宅での保育に手当はいくら出るのか? 具体的には、国からの手当は3歳以下の子ども1人に対して毎月350.27ユーロ(2021年現在)。私の友人の場合は上の子も同時に在宅で育てていたため、自治体独自の保育手当などが加わると月あたり約6~7万円ほどを受給していた。
こういった手当は保育者が祖父母の場合でも受給可能だ。自宅での保育はお金をもらうのに値する立派な仕事であり、それは「自宅で保育という大変な仕事をしてくれてありがとう」という国による感謝のメッセージにも見える。 この在宅保育手当は給与よりは少ないが、無給になるよりはよっぽどいい。実際、2018年には82%の家庭が一定期間、在宅保育手当を利用している。 一番多かったのは子どもが1歳半になるまで受給したというもので、最長期間の子どもが3歳になるまで利用する人は、年々減少していて約10%。利用者は決して多くはないのだが、休暇が切れるから、仕事がなくなるから、新学期が始まるから……と慌てて保育所に入れるのではなく、親と子どもの心と体の準備ができたところで預けることが可能になる制度だ。
実際、保育利用の割合を見ても、子どもが1歳未満で預けている家庭はわずか0.9%、2歳未満で36.8%だ。女性の就業率も、子どもの年齢が3歳未満の場合には48.2%と一時的に低くなる。これは他の北欧諸国と比べても、かなり低い。 年々、在宅保育の割合は減少し、女性の就業率は上がっているが、こういった制度が女性のキャリアの妨げになっているのではないか、という議論は常にある。在宅保育手当撤廃に関する提言は、国内外から聞こえてくる。この手当の利用者はまだまだ母親であることが多い。
フィンランドの子ども家族を支える制度は、幼児の親に柔軟で幅広い選択肢を与えている一方で、現実には母親が自宅で保育をする方に向かわせているのではないかという批判は、ある面から見れば事実だ。 そこで、ここ最近は自治体の保育手当は撤廃、もしくは支給期間を短縮する傾向にある。例えばトゥルク市では既に撤廃されているし、ヘルシンキ市は1歳まで、その隣のヴァンター市も1.5歳までとなっている。 ■社会も企業も2、3年の休職に寛容
それでも、在宅保育制度の満足度は高い。しかもフィンランド統計局の調査によると、子どもが3歳以上になると女性の就業率が80%を超え、小学校に通う年齢になれば、89.4%(2019年)にまで上がることから、利用者は元の職場に復帰しやすく、社会も企業も2、3年の休職に対して寛容なことがうかがえる。 実際、私の友人は育休と夫の海外赴任への同行で合計6年間休職していたが、その間に会社が合併し、元いた部署がなくなってしまった。復職時にはどこかの部署に仕事復帰することもできたのだが、彼女は思いきって社内公募されていたポジションに応募して見事選ばれた。元の仕事よりも昇進した形で復帰したわけだ。
同じように他の友人も、3人目の育児休暇を終えて、他社の部長職に応募して仕事復帰と転職、より責任のある仕事へのステップアップを同時に叶えていた。 産休・育休で欠員が出た場合、雇用主は代わりの人材を雇い、周りにしわ寄せがいかないようにするのが通常だ。しかもそれが半年や1年ではなく2~3年となれば、経験の浅い若者にとっては経験や実力をつけ、能力をアピールする好機になるし、企業にとっても新たな人材発掘のいい期間となり、うまくいけば正社員として採用する道も拓ける。
このように賛否両論ある在宅保育の制度だが、今のところは大きく変化する様子は見られない。ただ、今後は徐々に利用は減るのではないかと推測されている。いずれにしても、どの保育形態でも公的支援が得られ、親の選択肢が広いことはフィンランドの特長である。 ■共働きを前提とし、配偶者控除はなし 保育所の確保や在宅保育手当以外にも多種多様な支援制度がある。例えば、子どもが17歳になるまで一定額を支給する児童手当があるし、産休・育休も1960年代以降に充実し、父親も休暇が取れるように時代と共に変わっていった。
税制にも変化があった。1976年には扶養控除や配偶者控除を撤廃し、夫婦であっても1人ひとりに課税をする「個人単位課税」が導入された。 これは配偶者の収入状況が自分の所得税に影響しないことを意味していて、日本のようにパートで働いて年収を抑えた方が世帯としては節税になるといった状況が成り立たないことを示す。それよりも男女にかかわらずフルタイムで仕事をし、納税することが求められるようになったのだ。 北欧諸国の社会に詳しい東洋大学の藪長千乃教授も私の取材に対し、「福祉国家と女性の社会参加の関係には、税制が影響している」「個人課税方式の導入で、専業主婦やパートで働くことへのインセンティブがなくなりました。実は、夫婦単位での税制は、いまだにヨーロッパでは多くの国で選択的に使用されています。日本は個人単位の税制となっていますが、扶養控除制度や社会保険制度での非課税配偶者の優遇など、実質的には夫婦単位課税に近くなっており、女性が補助的な労働者となることを固定化させています」と語ってくれた。
さらに、1970年代、職場での男女差別を禁止する法律ができたことで、女性は牧師や軍隊の幹部以外であればどんな仕事にも就けるようになった。現在は、全ての職業で性別による制限はない。 政治の世界でも、かつては社会保健大臣や教育大臣が女性議員のためのポストで、財政大臣や国防大臣は男性という暗黙の了解があったが、1990年代からは女性も財政や国防の大臣職に就くようになり、男女間での暗黙の壁が壊れ始めた。また、大統領選にも女性が出馬して、男性候補者とほぼ変わらない投票数を獲得するようになっていった。(東洋経済オンラインより)